| THE THEATER OF DIGITAKE |
| ■前話の最終ページ |
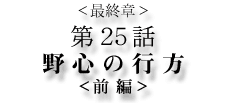 |
| ■幼なじみ 宮田浩一郎と木下昭夫は、幼稚園から中学校を卒業するまで机を並べた仲だ。 北海道の寒村での話だから一学年あたりの人数も少なく、実際に机が並んだ時間も長い。 木下の実家は、おもにロシアからの乾物などを輸入している小さな店だったが、コツコツ貯めていた金を株に当ててひと儲け。 その金を元手に貴金属の輸入販売をはじめてから小さな店は会社になり・・・。 ひとり息子の昭夫が中学を卒業するとと同時に家ごと会社を東京へ移した。 地方公務員を父に持つ宮田と違い、木下は恵まれた経済状態の中で少年時代を過ごしていた。 ほしいオモチャはすぐに買ってもらえるのはもちろんのこと・・・。 北海道の片田舎のオモチャ屋では、とても手に入らないような珍しいオモチャまで、わざわざ取り寄せてもらっていた。 そんな木下は同級生の間でも羨望の眼差しで見られていたし、着ている服も田舎にしてはわりとオシャレだったので、女の子の人気もあった。 しかし、木下自身は幼心にも、こうしてまわりに集まってくる連中が自分のところではなく、実は自分が持っている物に引き寄せられているということを本能的に知っていた。 だから、立つか這うかの時分から仲良しだった宮田のことは、いくらまわりに友達が大勢いても大事に思っていた。 2人が東京で再開したのは、宮田が大学進学のために上京して間もなくの頃。 東京にいる知り合いと言えば木下しか知らない宮田は、すぐに連絡をとった。 しかし、そこで再開した木下は父親の仕事を手伝って、すでに社会人となっていたし、会わないでいた数年間にすっかり都会的なイメージに変わっていた。 立場の違いをハッキリと認識してからというもの、話が合わなくなってしまった2人は・・・。 せっかく近くに住むことになったというのに、昔のように連むことはなくなった。 2人が久しぶりに連絡を取り合ったのは、お互いの結婚式の時くらい。 そして、父親から任された別会社が絶好調だった時に、たまたま再開。 やがて会社を倒産させた木下は、左遷が決まった宮田を誘って、人生の再起をめざそうとしている。 信じられるのは、やっぱりお金じゃない。 幼心に感じた、あの思いを信じて・・・木下は宮田に連絡をとった。 |
| Next■ |