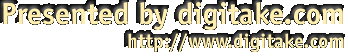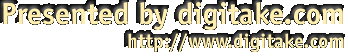一休さんといえば、とんち話で有名なユーモアあふれる僧侶。
活躍していたのは、今から約500年以上前の室町時代中期のことだ。
6歳で寺に預けられ、禅僧としての修行を積むが、16歳の時には、身分の高い和尚たちが位と金銭のために堕落し、仏の道からはずれていることを非難。
その後は"こじき行脚(あんぎゃ)"をして、あてのない旅を続け、最終的には京都・薪村の貧乏寺に住み着いて87歳まで生きた。
一休という名前は、修業先の和尚が「人生には苦しいことや悲しいことがいろいろあるが、それも一休みしているうちに過ぎ去っていく」という意味から名付けたもので、一休自身、その教えを生涯全うした。
一方、正月でにぎわう町にシャレコウベをぶらさげて現れ「人は誰でもいつか死ぬ。うかれてばかりいるな」と人々を戒めた・・・という一面もある。
変わり者と言えば、変わり者だが、決して権力にこびなかった一休は庶民の人気を集めた。
得意な禅問答や風変わりな教えは、口コミで広がっていった。
江戸時代に入って『一休咄』という本になったが、中には実際に一休の話かどうかが疑われるものも多いらしい。
一休の生涯でカタチに残る一番の功績は、京都・大徳寺の再建だろう。
応仁の乱によって焼け落ちた大徳寺の和尚を一休が命じられたのは81歳の時。
権力嫌いの一休は、寺の再建をはたすと、さっさと大徳寺の和尚をやめてしまったという。
その大徳寺に一休の遺言状が残されていた。
一休は臨終の際「この遺言状は、将来、この寺に大きな問題が起こった時に開け。それまでは決して読むな」と言い残していた。
僧侶たちは、その教えを守り、決して遺言状を開くことはなかった。
一休の死後、さまざまな問題が持ち上がる度に「いざとなれば一休和尚の遺言状が解決してくれる」という安心感もあっただろう。
一休の遺言状が、とうとう開かれることになったのは、死後100年を経た後の話。
すがる思いで開いた遺言状には、こう書かれていた。
「なるようになる。心配するな」