| THE THEATER OF DIGITAKE |
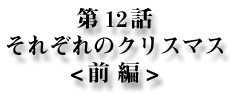 |
| ■宮田浩一郎の初恋 宮田浩一郎にも初恋の思い出はある。それは彼がダンドリー宮田と呼ばれる40年も昔のことだ。 小学校1年生の頃。相手は"王道"に従って隣の席に座った女の子だった。ちょっとふっくらと太った感じの娘だったことは記憶にあるが、それ以上はあまりよく覚えてはいない。消しゴムを忘れて来た時に貸してくれた・・・その程度のこと。 ただ、それが初恋だと思えるのは、クリスマス会のプレゼント交換の時に、その娘が持ってきたハンカチが当たったのが、すごく嬉しく感じたからだ。 その後も何となく気になる女の子はいなかったわけではないが、それはたまたま席が近かったとか、班がいっしょだったとか・・・接する機会が多かった相手に対して感じる親近感のようなもので、本格的に恋と言えるものを実感したのは、声変わりが終わってから後・・・ちょうど今の息子と同じくらいの年頃になってからだ。 相手は・・・やっぱり年上の女。 時代も環境もまったく違うというのに、どうして親子というものは、こんなに似てしまうんだろう。かつて、三村しよりに尋ねられた時には、照れくささもあって「忘れた」なんて言ってしまったが、その強烈な印象はとても忘れることはできない。 年上とは言っても、せいぜい2つか3つ上程度のことだから、相手も16、17歳・・・まったくの子供だったに違いない。ところが、今では30歳になる部下も子供に思える年だというのに、あの時の彼女のことを思うと、充分に中年となった今の自分をもっしても何だか手玉にとられてしまうような気がするから不思議だ。 彼女は高校生でも子供でもなく・・・確かに女だった。相手に女を感じた時、自分も男になれた。 とは言え、彼女との間にあったのは、ただ一度、彼女の細い指が自分の唇に触れて「ダ・メ・よ」とささやいたくらいの思い出で、その先何があったわけでもないのだが・・・。 妻に出逢って、結婚してからこの方、その彼女の夢を見ることはなくなった。 小学校の頃の初恋相手と同様に、彼女の顔かたちも懸命に考えなければ思い起こすことすらできない。ただ、あの時の唇の感触と近づいてきた彼女の女の臭いだけがフッとよみがえることはある。 そして、夢の中でその感触とゴチャまぜになって出てくるのは、例外なく三村しよりの顔だった。 |
| Next■ |